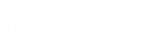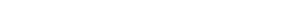中村春子
「鳥肌が立った」。寄り道して通った千葉市若葉区の団地の一室から、「ペンペンッ」と聞き慣れない音が漏れてきた。当時、小学一年生だった中村春子さん(27)は一度帰宅し、母の正子さんを連れてその場へ舞い戻った。「あの音は何?」と尋ねる娘に、「三味線だ」と答えた母はこう直感したに違いない。「血が騒いだ」。まだ三味線という楽器の存在すら知らない娘。その血筋はというと母方の曾祖父(加藤秀一)、祖父(加藤正八)ともに三味線奏者だった。 「親から三味線を買ってもらってからは、先生について毎日練習しました。中学生の時にはプロになろうと決めました」 ■栄誉とスランプ 地元の県立泉高校に進学後は、夏冬の休みなどを利用して「たたき三味線の名人」とうたわれた故・山田千里(ちさと)氏に師事。青森県弘前市まで見習い修行に出かけた。同校卒業後は弘前市に移り住み、二〇〇二年までの四年間、師匠の下で修行した。 「芸を盗んで、さらにどうそれを自分のものにするか。ただコピーしていてもダメ。先生からはプロとしての姿勢や、仕事のやり方全般を学びました」 〇一、〇二年には「津軽三味線全国大会」A級女性部門で二連覇達成。その後、優れた女性アーティストに贈られる「エイボン芸術賞」も受賞。はた目には飛ぶ鳥を落とす勢いに見える時期だが、本人の思いは違う。 「今振り返ると弘前にいたころが最もスランプでした。チヤホヤされていい三味線は弾けていなかった。自分を見失っていたと思います」 弾けばお金になった。マスコミの取材も急激に増えた。周囲の嫉妬(しっと)も強まった。ただ真摯(しんし)に三味線と向き合いたい-。そんな思いが日々募っていった。 ■原点を見つめて 〇二年の十二月に青森を離れ、一時東京の芸能プロダクションに所属。CD「春子」をリリースした。その後、故郷の千葉市に戻り、三年ほど前から八街市に移住。ようやく津軽三味線の原点を見つめる時を得た。 「うまく弾こうとするとかえってダメ。今まで練習してきたことを出すようにすればいい。練習以上のことは本番では出ないと思います」 「最近はテレビの番組などで速くガチャガチャと弾く人が目立ちますけど、それだけが津軽三味線ではない。もともとは生活の中に溶け込んだ、ゆったりとした音なんです」 約百五十年ある津軽三味線の歴史に思いをはせる。曾祖父や祖父、その友人だった高橋竹山(初代)ら、先達への敬意も強まる。 「今年の春に青森へ行ったんです。古い型の、ゆったりとした演奏をしたら地元の人が泣いて喜んでくれた。昔ながらの『生活の中の音』を残していかなければ」